快眠がもつ健康効果!睡眠の5つの役割

「健康で入るためには良い睡眠が重要」なことは、誰でも知っています。
ただ知っていても仕事が勉強などで何かと忙しかったり、スマホやゲーム、交友に夢中で、現代人は睡眠不足で健康を害しています。
特に子供の睡眠不足の問題は重大で、勉強や身体の成長に問題が出ます。
厚労省「国民健康・栄養調査」のデータによると学生の低身長化が加速しているとか。
そこで睡眠がもつ5つの役割を紹介。快眠の健康効果について見てみましょう。
体と脳を休ませる
人は睡眠をとらないと覚醒時のパフォーマンスが著しく低下します。
この原因は、人間の体は意思とは関係なく自律神経が常に働いており、活動モードとリラックスモードの切り替えがされないことにあります。
日中は活動モードである「交感神経」が優位で、体内の血糖値と血圧、脈拍が上がり、筋肉と心臓の動きが活発になりますが、活動モードでは体と脳に疲労とストレスがたまります。
逆にリラックスモードの「副交感神経」が優位になるのが、ノンレム睡眠中と食後です。
なので、交感神経と副交感神経を切り替えて、体と脳を休ませるために寝る必要があります。
また、体や脳の疲れやストレスが取れない人は、夜になってスムーズに副交感神経優位の状態に移行されていないため、寝つきが悪く、眠りも浅くなることが原因です。
記憶を定着させる
学習後に睡眠をとることで記憶が定着することを知っている人も多いでしょう。
睡眠と記憶についての研究では、次のような概念が提唱されています。
- レム睡眠中:いつ、どこで、何をしたか、エピソード記憶を固定される。
- 深いノンレム睡眠:イヤな記憶を消去する。
- 浅いノンレム睡眠:体が覚える記憶が固定される。
このように睡眠中にノンレム睡眠とレム睡眠を繰り返すことで、記憶が整理されて、定着します。
そして、記憶が定着されるだけでなく、イヤなことや不要なことの記憶は忘れることも大切なので、睡眠中に記憶の消去も行われます。
ホルモンバランスを調整する
脳はホルモンのバランスを制御していますが、睡眠不足だと脳の働きも悪くなり、ホルモンバランスも崩れてしまいます。
たとえば睡眠時間を削ると、脂肪細胞から分泌される「食欲を抑えるレプチン」が減少し、胃から分泌される「食欲を増すグレリン」が増加します。
他にもグロースホルモン(成長ホルモン)は、深いノンレム睡眠時にもっとも多く分泌されます。
このグロースホルモンは、子供の身体の成長に関与し、大人でも細胞の増殖や代謝を促進するなど、アンチエイジング効果が知られています。
また、生殖や母性行動に関与する「プロラクチン」も深いノンレム睡眠で多く分泌されます。
そして、この「グロースホルモン」や「性ホルモン」の影響を受けるため、肌の水分と睡眠は密接な関係があり、皮膚の保水量は睡眠で上がります。
このように睡眠はホルモンバランスを調節しており、研究では良い睡眠は生活習慣病の改善につながることもわかっています。
免疫力を上げて病気の改善と予防する
睡眠はホルモンバランスと密接な関係があり、ホルモンバランスの崩れは免疫の働きを悪くします。
なので睡眠は免疫力を向上させて病気の改善と予防する役割もあります。
例えば、「風邪は寝て治す」というように、風邪の症状を抑える薬はあっても風邪を治す薬はないため、風邪を治すには睡眠で休息をとることが理にかなっています。
他でもインフルエンザのワクチンを予防接種しても、睡眠が乱れると免疫が確立せず、ワクチン接種の効果がなくなることがあります。
また、リウマチなどの自己免疫疾患やアレルギーも、睡眠時に免疫増強がきちんと働いていないとアレルギーが悪化する危険もあります。
脳の老廃物を排出する
脳は直接、頭蓋骨に収まっているのではなく、「脳脊髄液」という保護液のプールに使っています。
なので、頭を打っても脳が傷つかないのは脳脊髄液のおかげです。
脳脊髄液の量は、およそ150ccほどであり、1日4回(合計600cc)も入れ替わっています。
研究によると、この脳脊髄液が入れ替わるとき脳の老廃物も一緒に除去しています。
つまり、脳脊髄液を入れ替えることで脳をメンテナンスしているのです。
この脳のメンテナンスは、覚醒時も行われていますが、それだけでは追いつかないので、睡眠時にまとまったメンテナンスが行われます。
もし睡眠不足によって脳の老廃物が脳内にたまってしまうと、脳のダメージにつながり、認知症発症のリスクが促進されます。
マウスの研究では、アルツハイマーになりやすい遺伝子をもったマウスの睡眠を制限すると、「アミロイドβ」というアルツハイマーの原因物質のひとつがたまりやすくなることがわかっています。



















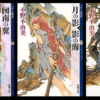

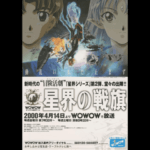
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません